2010年02月11日
踵の痛み
バレーボールの障害でなにが多いのか、少し調べたところ、一番多いのが捻挫のようです。
バレーボールをしているこに聞いたところ、ほとんどの選手が捻挫をしているようです。
アイシングとテーピングだけでは、激しい練習を続けているのでは、なかなか完治しません。
バレーボールのようなジャンプをする競技では、捻挫とよべるのかどうかですが、
ジャンプしたあとカカトから着地してしまい、踵骨(しゅこつ カカトの骨)が上方に変位してしまい、
足首の可動域が制限され、足首の甲や、その他の足関節部位に痛みが生じることがあります。
この場合、じんわりと足首を牽引し、早いうちにカカトを引き出さなければなりません。
アスリート大歓迎です。
blog 肩の凝らない話
「からだコンディショニング」
※地図はこちら
※メールお問い合わせ
ご予約は:073-494-4301
診療時間10:00~22:00
休み不定休
和歌山県和歌山市のカイロプラクティック整体院|"からだコンディショニング"
和歌山カイロプラクティック整体院/ からだコンディショニング

2009年06月16日
耳がわく
柔道の寝技で耳がわくというのは、しばしば起こりえます。
正式名称はカリフラワーイヤー、どういった症状なのでしょうか。
耳の皮膚と軟骨の間に内出血を起こし、血液がたまって腫れたのが耳介血腫です。
そ
柔道から総合格闘技に転向した石井慧選手は両耳が、格闘家として勲章のごとくわいていますね。
原因
耳介の反復する摩擦刺激や打撲で生じます。また、特に外傷の原因がなく発症することもあります。
症状
発症直後は耳介前面の軟らかい腫れですが、放置しておくと血腫は徐々に硬くなり耳介は大きくなります。
さらに再発を繰り返すことにより最後はこぶのように硬くなり、耳介変形を呈してきます。
病院で治療
発症直後で腫れが軽度のときには冷湿布程度で良くなることもあります。
太い注射針で刺して、血液をひんぱんに抜きます。
血液が固まって十分抜けないときは皮膚の小切開を追加して抜きます。
抜いた後は予防のために圧迫固定しておきます。
抜かずに柔道で受傷を繰り返していると、次第に血腫は硬くなり処置では治らなります。
私も遠い昔7,8年柔道をして、右耳だけ少しわいています。
といっても触ると耳が厚く、硬い程度ですが。
むしろイヤホンが右耳だけ抜けにくくていいくらいです。
発症時は触れるだけでも、飛び上がるほど痛かったですが、病院にも行かず、
そのまま練習を続けていたと思います。
昔は根性があったのでしょうね。
また熱心に寝技の練習をしたものがなる、といわれてましたが、ならない人もいます。
今は専用の耳に触れないパッドなんかがあるようですが、
昔はガムテープの穴を耳にすっぽり固定して、くくりつけていました。
ガムテープの芯自体硬いものですので、耳に触れると、よけいに痛かったのを思い出します。
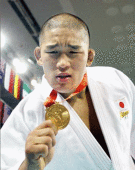
"石井慧のデビューはいつなんだろう。"
「からだコンディショニング」
※地図はこちら ※メールお問い合わせ
電話予約073-494-4301
診療時間am10~pm10:00 休み不定休
パソコンからホームページはコチラ
mobile site Fc2 mobile site
ブログ「肩の凝らない話」もどうぞ
2009年06月15日
頸髄(けいずい)損傷
死因は頸髄(けいずい)損傷で、首の骨の内部までズレて中枢神経を損傷した、
という事が分かりました。
頸髄(けいずい)損傷
頸髄とは
背骨の中には脊髄(せきずい)という、大きな神経の束があり、手や足を動かしたり、
痛みや温度などを感じたりする神経の元で、脳とつながっています。
この脊髄の頚椎(首の骨)を頸髄といい、首の骨の中にあります。
頸髄からも頸神経とよばれる大切な神経が8対のびて、それぞれが身体の運動や知覚を分担しています。
脊髄が損傷すると、そこから下にある神経が麻痺するため、体が動かなくなり、皮膚の感覚もなくなってしまいます。
損傷部分が、脳に近いほどマヒする神経が多くなり、それだけ障害も重くなります。
頸髄の場合、ほんの少し傷つくところが違うだけで、動くところや感じるところが大きく変わります。
損傷程度によって、完全麻痺や部分的に動かない不全麻痺になります。
症状
運動機能 ・・・胸から下は動かすことができず、歩けません。
知覚機能・・・麻痺した部分の感覚、温度の感覚がありません。
体幹機能・・・座った姿勢を保てません。
自律神経・・・汗が出ないため体温調節が困難です。
排泄機能・・・通常通りできません。
身体を起こすと血液が下に下がってしまい、貧血をおこしやすくなります。
"レスラー三沢光晴さんのご冥福をお祈りします。"
「からだコンディショニング」
※地図はこちら ※メールお問い合わせ
電話予約073-494-4301
診療時間am10~pm10:00 休み不定休
パソコンからホームページはコチラ
mobile site Fc2 mobile site
ブログ「肩の凝らない話」もどうぞ
2009年05月21日
肉離れ2
「肉離れ」
肉離れの症状
筋肉線維の断裂のない軽い肉離れ
・足に違和感、重くてけだるいような不快感
筋肉線維が断裂した肉離れ
・腫れ、肉離れの部位を触ると痛い
・足の場合は、歩くと痛い
完全に筋肉の線維が断裂した肉離れ
・断裂している箇所が、へこんでいる
・腫れがひどい、痛みも大きい
一般的に一番発生しやすい部位は、ふくらはぎの肉離れです。
肉離れを起こしたら
・筋線維の断裂なので、その筋肉を動かさない事です。
・断裂の部位に腫れが生じますので、アイスパックで冷却します。
・テーピングで固定して、断裂が回復するしかありません。
・以上は応急処置ですが、一度病院で見てもらいましょう。
痛みがある時は、ストレッチなどで筋肉を伸ばしてはいけません。
痛みがおさまってきてから、、ストレッチをおこないましょう。
基本的に肉離れが起きる前に、予防をしておくことが重要です。
テーピングなどで予防して運動をしましょう。
今日も時間がなく、「肉離れ」の説明が十分ではありませんでした。
機会があれば、もっと詳しく調べたいと思っております。
肉離れは予防をしましょう。
「からだコンディショニング」
※地図はこちら ※メールお問い合わせ
電話予約073-494-4301
診療時間am10~pm10:00 休み不定休
パソコンからホームページはコチラ
mobile site Fc2 mobile site
ブログ「肩の凝らない話」もどうぞ
2009年05月20日
肉離れ
「肉離れ」
運動をしている際、骨格筋の筋膜、筋繊維などの一部分が痛められてしまうことです。
走ったり、跳んだりなど、急激に強く筋肉を収縮、伸展させた場合によく起こります。
一つにまとまっていた筋繊維が、外部から無理な力がかかったせいで、部分断裂した状態です。
肉離れのしやすい部位は大腿部、下腿後ろ側、ふくらはぎ、上腕、肋間筋などです。
肉離れをしてしまったら、自分だできる治療としては、アイシングしかありません。
炎症が起きていますので、絶対に温めてはいけません。
軽い肉離れでも筋繊維の断裂です。
基本的には、切り傷や裂傷と同じで、固定しておけば自然にくっつきます。
肉離れの原因
・運動の動作で例えると、踏ん張る動作や切り替えしの動作の瞬間に発生することが多いようです。
・筋肉の収縮によって関節が曲げるという筋肉の収縮時ではなく、関節が伸ばし過ぎるのを抑える
ことによって、筋肉が引き伸ばしつつ収縮している時に起こるのが、肉離れです。
運動が急激すぎて、筋肉が収縮して切れることとあります。
・瞬間的に筋肉の繊維や膜が伸ばされて断裂が生じた状態で、運動中の筋肉に急激に強い力が
かかった時、予期しない動きをした時に生じやすい。
・運動不足の人の日常的な動作で起こることもあるようです。
・オーバーワークも運動不足も肉離れの原因となります。
筋肉が疲労しているときなどは要注意です。
予防にはウオーミングアップやクールダウン、十分なストレッチングを行ないましょう。
今日は時間がありません、「肉離れ」明日に続く
感染予防にマスクをしましょう、といっても売り切れてありません。
「からだコンディショニング」
※地図はこちら ※メールお問い合わせ
電話予約073-494-4301
診療時間am10~pm10:00 休み不定休
パソコンからホームページはコチラ
mobile site Fc2 mobile site
ブログ「肩の凝らない話」もどうぞ















































